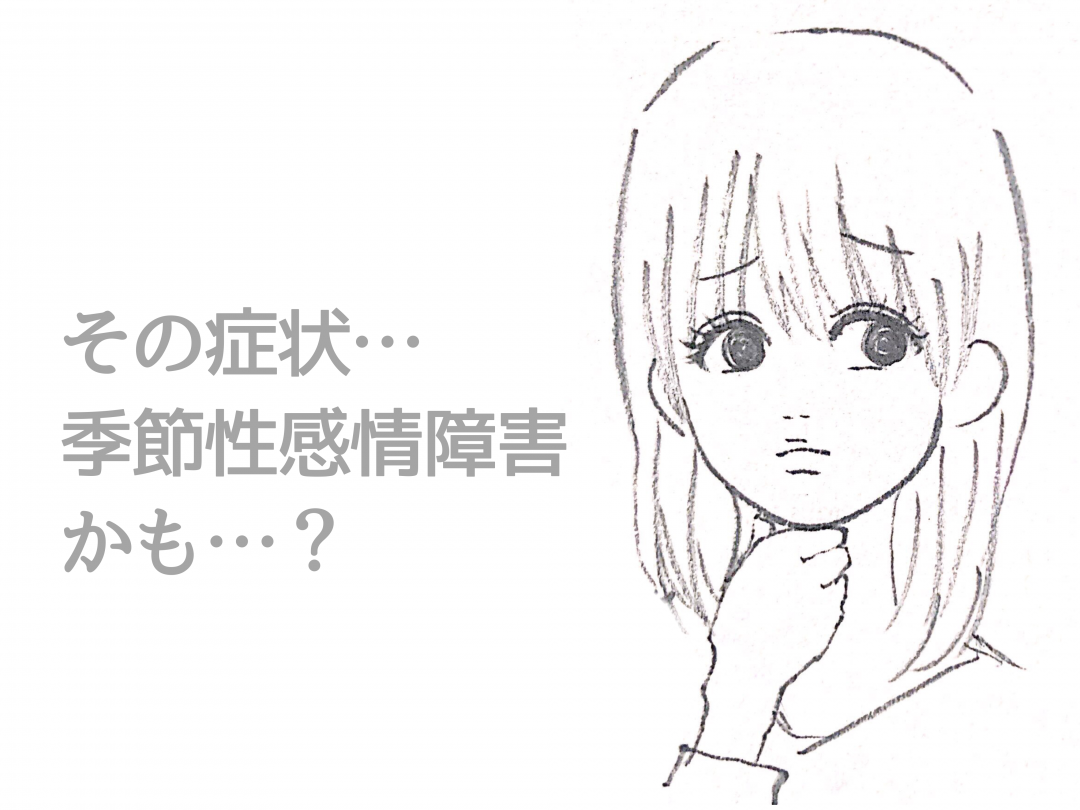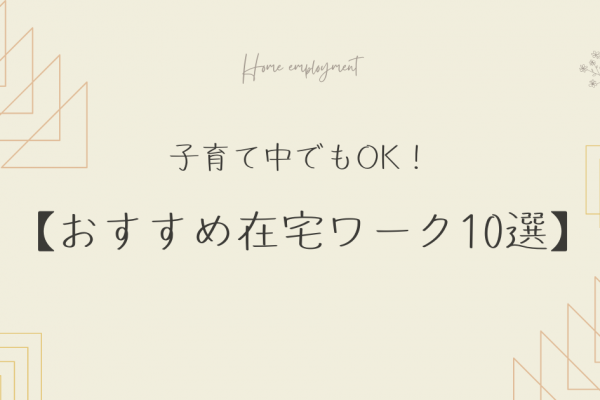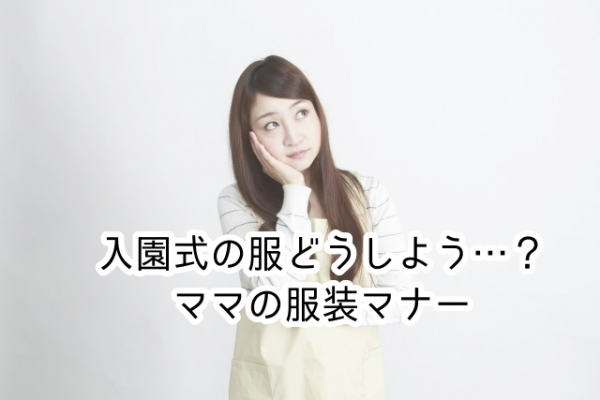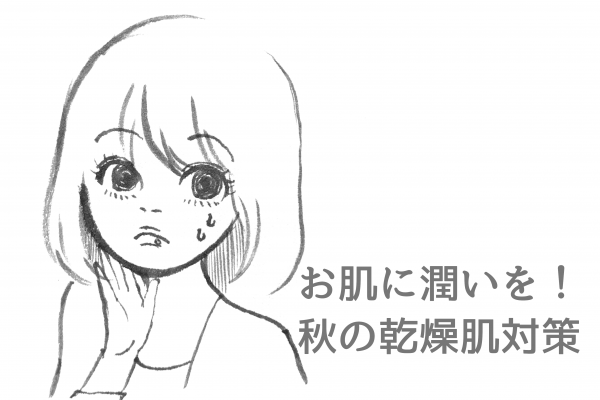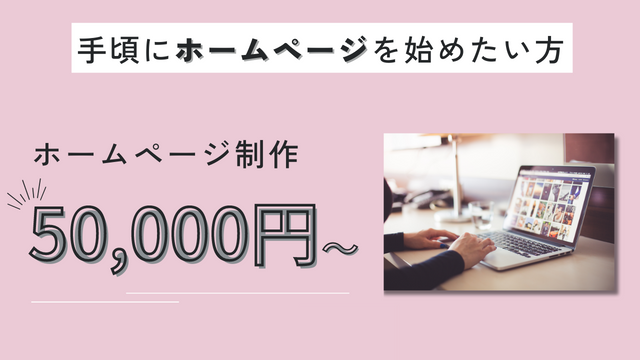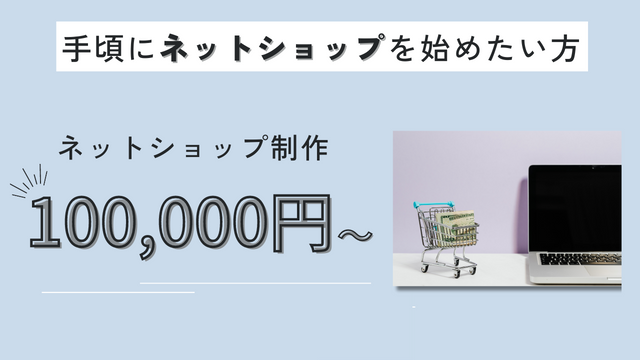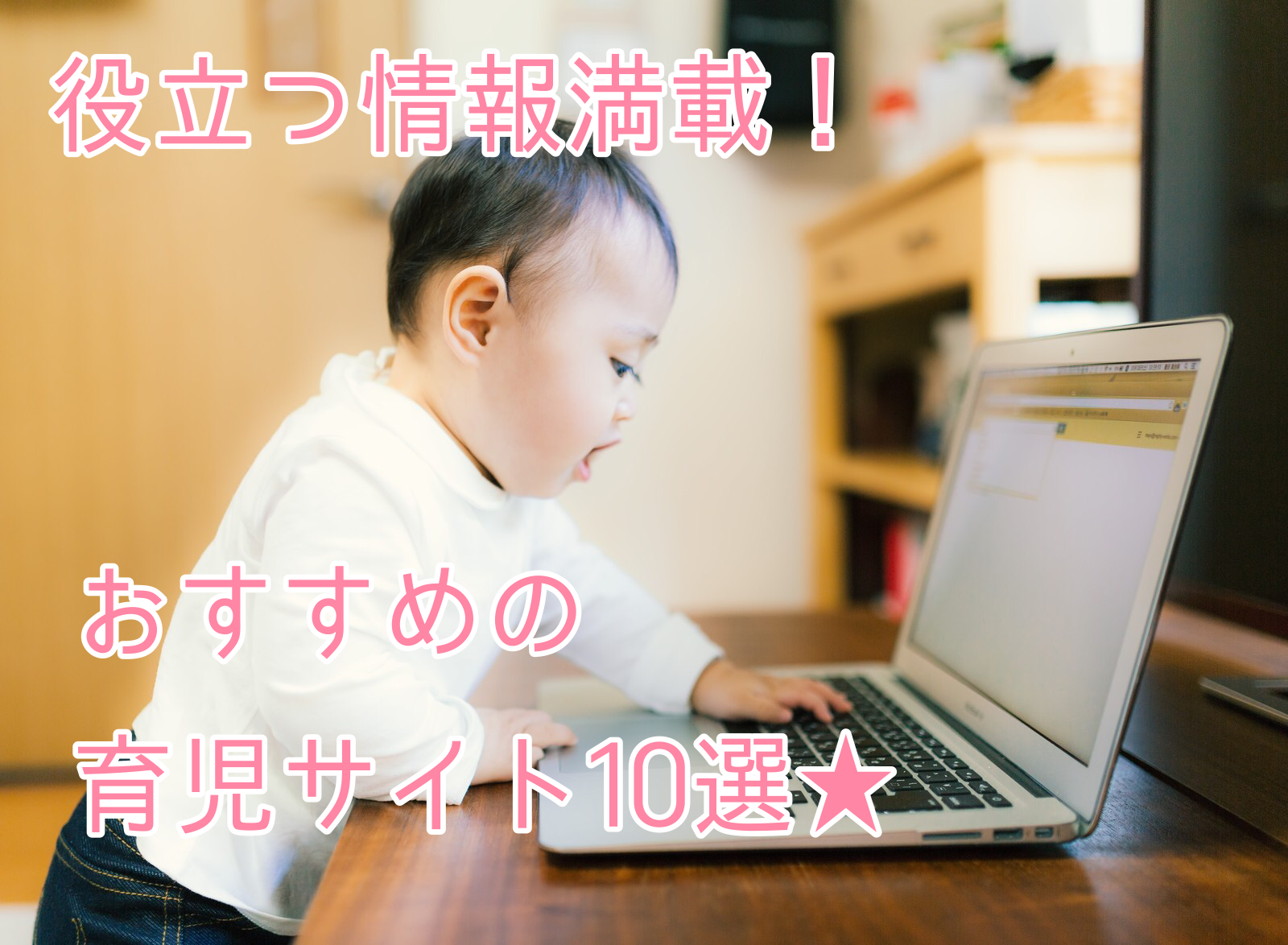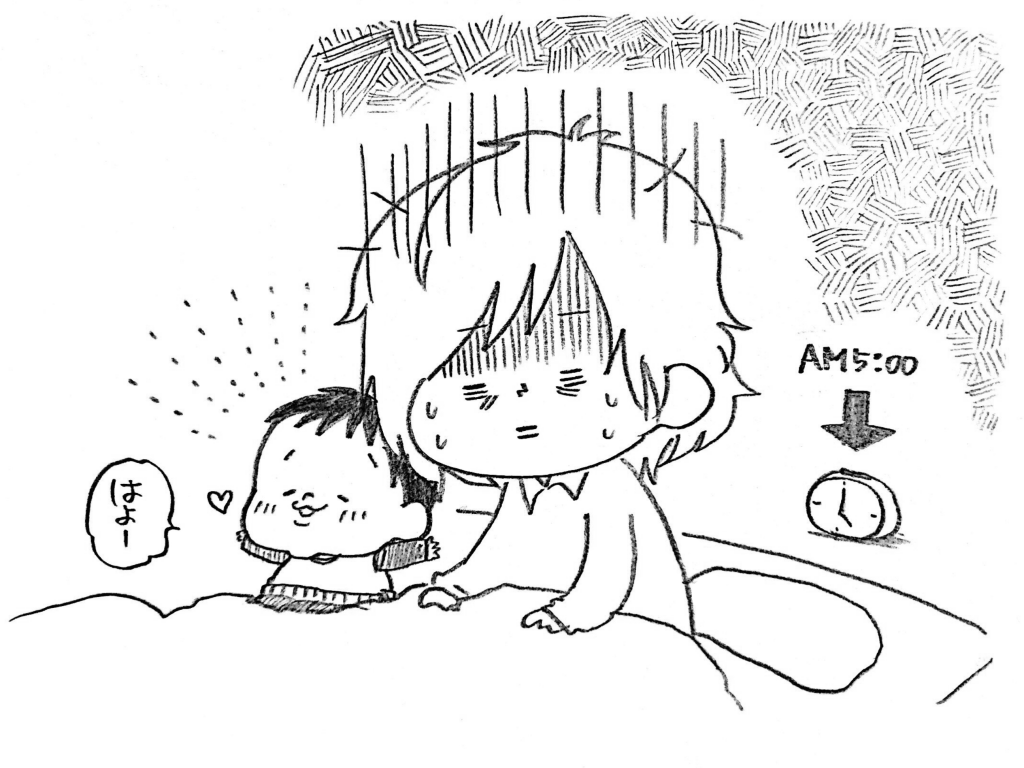「私、毎年秋になるとダメなんだよねぇ」
先日、姉がこんなことを言っていました。
毎年秋になると気持ちが落ち込んだり、体がだるくなったり、意味もなく焦燥感に駆られるそうなのです。
その時は「大変だね、無理しないようにね」と話したのですが、そのあと気になって調べてみると「季節性うつ病」「季節性感情障害(SAD)」「冬季うつ病(ウインダーブルー)」などの気になるワードが出てきました。
男性よりも女性の方が発症しやすく、妊娠可能な年齢の女性に多くみられる傾向があるそうです。
たしかに私自身も秋は一番センチメンタルな気分に陥りやすく、今までの人生を振り返ってもこの時期が一番しんどかった記憶があります。
もしかしたらあなたも該当するかもしれません。
症状や原因、治療法や予防法をまとめてみましたので参考になれば嬉しいです。
秋うつの症状

10月から11月にかけて症状が出て、3月ごろになると回復するこの秋うつの症状。
毎年この時期にだけやる気が低下したり、精神的に不安定になり、春夏と比べるとかなり生きづらくなるのです。
- 気分が落ち込む(特に午前中)
- 疲れやすく、体を動かすのが億劫になる
- 好きなことが楽しめない
- 集中力が落ちる
- 焦燥感に駆られる
- イライラして周りのものにあたる
- 過眠(普段より睡眠時間が長くなり、朝起きるのが辛い)
- 過食(炭水化物やチョコレートなどの甘いものが食べたくなる)
体がだるくなり運動量が減る上に過食に走ってしまうので、肥満になる人も少なくありません。
また、朝起きるのが辛くなり、午前中は気持ちも落ちてしまっているので昼夜逆転生活になってしまうこともあります。
5月から9月ごろに発症する「夏季うつ」というものもありますが、夏のうつは食欲低下、不眠の傾向があり、秋のうつは過食過眠の傾向があると言われています。
原因は日照時間の減少

お昼も3時を過ぎると日が落ちてきて夕焼け空に変わり、あっという間に真っ暗になってしまうようになりましたよね。
実はこの早い日没が、秋うつと大きく関わっているのです。
人間にはセロトニン、アドレナリン、ドーパミンの3つの神経伝達物質があり、そのうちのひとつのセロトニンは別名「幸せホルモン」と呼ばれ、自律神経を整えます。
セロトニンは日中の太陽光を浴びることによって作られるのですが、秋冬は日の出が遅く、日の入りが早い為、太陽の光を浴びる時間が春夏に比べて少なくなり、セロトニンの分泌が減少してしまうのです。
オーストラリアでは晴れの日と曇りの日とでセロトニンの分泌量に差が生じているという研究結果も発見されました。
また、セロトニンが減少すると体内時計が乱れてしまうのです。
人間には睡眠と覚醒やホルモンの分泌を整える「概日時計」という機能が備わっており、その調節はメラトニンというホルモンが行っています。
睡眠ホルモンであるメラトニンはセロトニンを原料とし、不足することで変調をきたしやすくします。
日照時間の変動から幸せホルモンのセロトニンと、睡眠ホルモンのメラトニンが減少し、気分が落ちて体のリズムも狂ってしまうのです。
それが秋うつの大きな原因となっています。
治療法
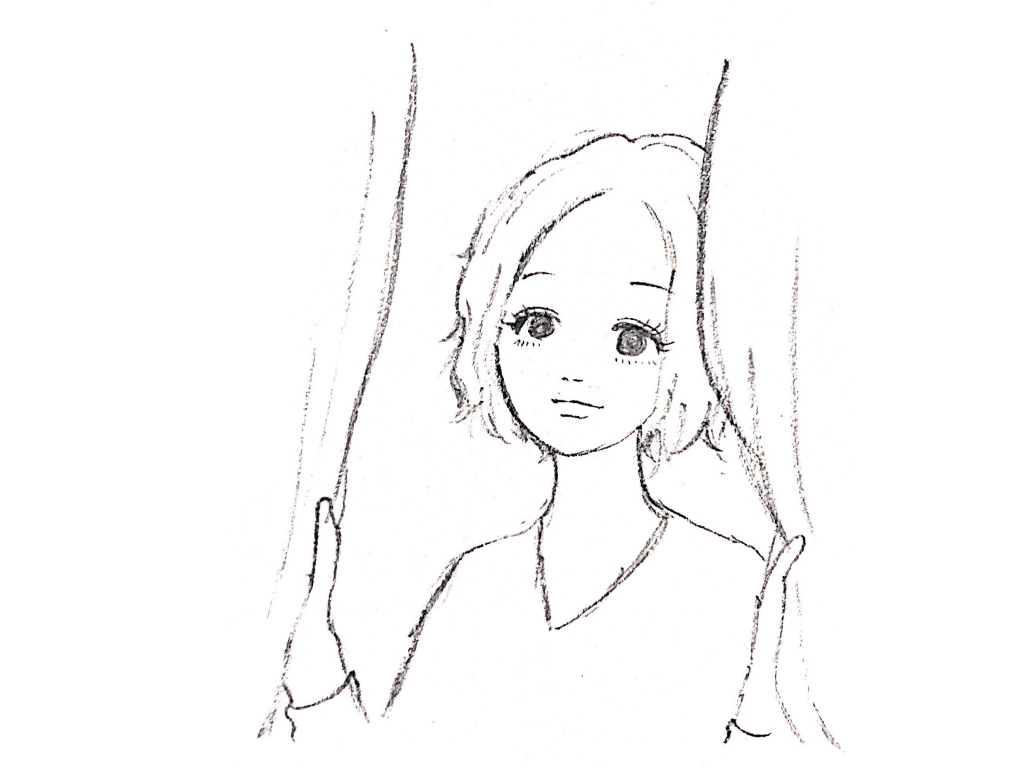
この季節性のうつ病に一番効果的なのは太陽の光を浴びることです。
実際に季節性感情障害と診断された方が医師からの指導で、出勤前の約1時間、日光を浴びながら近所を散歩すると症状が改善されたそうです。
ウォーキングや通勤時間を利用して太陽の光を浴びることが一番治療に繋がります。
太陽が昇る前に出勤し、暗い時間に帰るという方はランチタイムの時だけでも外に出て太陽を浴びたり、自宅や職場の照明を明るいものに替える等して、とにかく積極的に光を浴びましょう。
疲れて休日は家に引きこもってしまいたいところですが、朝起きたらカーテンを開け、午前中に一度は外に出て太陽の光を浴びるように心がけてください。
症状が重い場合は、ライトボックスによる光治療や抗うつ薬などの治療法がありますので、一度受診されることをオススメします。
秋うつにならないための予防法
季節性に関わらず、うつ病は誰にでも起こり得る病気です。
今は大丈夫と思っていてもいつか発症したり、重症化してしまうかもしれません。
それを防ぐためにも、普段の生活習慣を見直し、予防策を張っていきましょう。
栄養バランスの良い食事
セロトニンの分泌には太陽光だけでなく、普段の食事も大変重要となっています。
セロトニンを体内で生成するために必要な栄養素は、必須アミノ酸であるトリプトファン、炭水化物、ビタミンB6の三つです。
トリプトファンが含まれる食材
- 大豆製品(豆腐、納豆、味噌、醤油、豆乳、きなこetc…)
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、チーズetc…)
- 鶏卵
- 魚卵(タラコ、スジコ、明太子etc…)
- ゴマ、ナッツ
炭水化物を含む食材
- 穀類(ご飯、麺類、パンなど)
- いも類
- 果物
ビタミンB6を多く含む食材
- 魚類(サケ、サンマ、イワシ、マグロ、カツオ、サバetc…)
- にんにく、しょうが
- 未精製の穀類(玄米、胚芽パンetc…)
- 豆類(大豆、ヒヨコ豆、レンズ豆etc…)
メラトニンが分泌されるまでには少し時間がかかるので、トリプトファンは朝食に取り入れるのが効果的です。
特にバナナはトリプトファン、炭水化物、ビタミンB6の3つの栄養素すべてが含まれているため、一番手軽に取り入れることができます。
もちろん、バランスよく食べることが重要です。
適度な運動
運動をすることでドーパミンの分泌を促すことができます。
簡単に言えばアドレナリンは「やる気のパワー」で、倦怠感やイライラを改善する効果を得ることができます。
自宅で簡単にできるヨガでも良いですし、太陽の光を浴びるためにもウォーキングをしたりすると良いですね。
感情のアウトプット
辛い、しんどいと思う感情を自分の心の中だけで留めておくことは非常に危険です。
自分の感情を素直に話せる相手を見つけることが心のデトックスになります。
直接人に話すのが難しければTwitter等のSNSを活用するのも良いですし、感情を吐き出せる環境を作るのも予防策の一つです。
スケジュールの管理
季節性感情障害の症状の一つに「仕事がうまく処理できない」というものがあります。
気力の低下や焦燥感から起こる症状ですが、うまくいかなければいかないほど負のループから抜け出せなくなってしまいます。
ToDoリストを作るなどして、スケジュールだけでなく心の整理をして落ち着かせることが効果的です。
まとめ
- 秋から冬にかけて「季節性感情障害」になりやすい(特に女性)
- 毎年この時期にだけやる気の低下、精神的な不安定に陥り、春頃になると回復する
- 日照時間の減少が大きな原因
- セロトニンの減少により自律神経が乱れる
- メラトニンの減少により体内時計が乱れる
- 太陽の光を浴びることが治療に繋がる
- トリプトファン、炭水化物、ビタミンB6の摂取を心がけた食事を摂る
- ウォーキング等の適度な運動をする
- 自分の感情を話せる相手を見つける
- スケジュールと心の整理をする
- 症状が重い場合は医師に相談する
冒頭に記述した私の姉ですが、症状が重いため医師に薬を処方してもらいました。
そのおかげもあり、わけもなく気持ちが焦ったり不安になる等といった症状は落ち着いたようです。
出勤時は徒歩、または自転車で行き、部屋の照明も明るいものに替えるなどして対策を取っています。
誰にでも起こりうることなので日常生活から予防することが大切です。
少しでも生きづらさを感じにくくなることを祈っています。